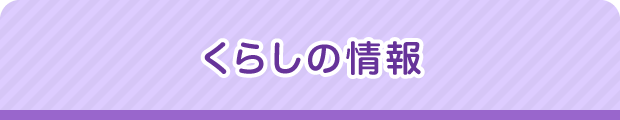児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
手当を受けられる方
次のいずれかに該当する児童(18歳になった年の年度末までの間にある児童または20歳未満で一定の障害の状態にある児童)を監護している母、父または父母に代わって児童を養育している方が、児童扶養手当を受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
手当を受けられない場合
手当を受けようとする方が・・・
- 国内に住所を有しないとき
- 手当を受けようとする方や、同居の家族(扶養義務者)の所得が一定額以上であるとき
- 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係があるとき(異性と同居したり、異性の頻繁で定期的な訪問等がある場合等)
児童が・・・
- 国内に住所を有しないとき
- 里親に委託されていたり、施設に入所しているとき
- 父または母と生計を同じくしているとき(重度の障害の状態にある場合を除く)
- 父または母の配偶者に養育されているとき(婚姻の届け出をせず、内縁関係(事実上の婚姻関係)にある場合も含む)
手当額 【令和5年4月現在】
所得金額によって手当額が異なります。
| 区分 |
児童1人の場合 (月額) |
児童2人目の加算額 (月額) |
児童3人目以降の加算額 1人につき(月額) |
| 全部支給 | 44,140円 | 10,420円 | 6,250円 |
| 一部支給 | 44,130円から10,410円 | 10,410円から5,210円 | 6,240円から3,130円 |
所得制限限度額【平成30年8月分から】
手当を受けようとする方または同居の家族(扶養義務者)の前年(1月から9月に申請する場合は前々年)の所得が以下の所得制限限度額を上回る場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の一部または全部が支給されません。
| 扶養親族等の数 |
【受給資格者】 全部支給の 所得制限限度額 |
【受給資格者】 一部支給の 所得制限限度額 |
【扶養義務者】 所得制限限度額 |
| 0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
- 6人目以降は、1人につき380,000円加算されます。
- 「扶養親族等の数」とは、住民税の課税台帳上の扶養人数です。
- 「扶養義務者」とは、直系の血族及び兄弟姉妹です。
- 受け取った養育費の8割相当額が所得に加算されます。
- 老人扶養親族等がいる場合には、所得制限限度額に一定額が加算されます。
支給時期
原則として、申請した月の翌月分から支給されます。
支給月は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支給されます。
ただし、申請後に内容を確認するための事務処理期間が必要なため、最初の支給月については遅れることがあります。
受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには、児童扶養手当認定請求書を提出する必要があります。
手当を受けようとする方のご家庭の状況により必要書類等が異なりますので、事前に保健福祉課子育て支援係へご相談ください。
必要書類等
申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本
- おおむね1か月以内に交付されたもの。
- 申請者と対象児童の戸籍が別の場合には、それぞれの戸籍謄(抄)本が必要となります。
申請者の世帯全員の住民票
- おおむね1か月以内に交付されたもの。
- 対象児童と別居している場合(単身赴任や進学のための下宿など)は、それぞれの住民票が必要となります。
申請者と世帯全員の個人番号が分かる書類
- 個人番号カード
- 個人番号の記載がある住民票など
申請者の本人確認ができる書類
- 個人番号カード、運転免許証など
- 本人確認書類について、詳しくはこちらをご覧ください→www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/7,2459,30,html
申請者名義の預金通帳
印鑑
その他、必要な届け出
- 現況届・・・受給資格を有する方全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出が必要です。手続きについては、個別にご連絡します。
- 額改定届・・・対象児童が減少したときに提出が必要です。
- 額改定請求・・・対象児童が増加したときに提出が必要です。
- 資格喪失届・・・受給資格がなくなったときに提出が必要です。
- その他の届・・・氏名・住所・銀行口座の変更、受給資格者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、新たに公的年金を受けることができるようになったとき、受給している年金額に変更が生じたとき等。
※届け出が提出されないと、手当の支給が遅れたり、受給資格がなくなったり、場合によっては手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
公的年金と児童扶養手当の併給について
公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給する方について、平成26年12月分以降、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
<児童扶養手当を受け取れる場合の例>
- 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合等
また、令和3年3月分以降、児童扶養手当の額が障害基礎年金等(国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金等)の子の加算部分を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。