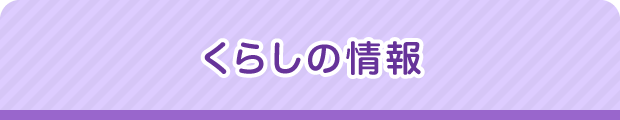保険料について
保険料の財源
後期高齢者医療制度では被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるための財源として保険料を納めていただきます。
後期高齢者医療の財源は、国や県・市町村からの公費が約5割、他の医療保険制度からの支援金が約4割、被保険者からの保険料が約1割という内訳で運営をしています。
| 被保険者からの保険料 約1割 |
公費 (国、県、市町村) 約5割 |
|---|---|
| 後期高齢者支援金 (他の医療保険制度からの支援金) 約4割 |
保険料について
被保険者から徴収する保険料の決定には以下の算定方法を用います。
| 年間保険料額 | = | 均等割額 (被保険者が均等に負担する部分が均等割額となります。) 被保険者一人当たり47,400円 |
+ |
所得割額 (最大43万)を除いた額×9.28% |
|---|
※賦課のもととなる所得が58万円以下の方は、所得割率8.72%となります。
※均等割額、所得割率は宮城県内で均一となり2年ごとに見直されます。
※保険料限度額は年額80万円です(障害認定を受けた方または令和6年3月以前に加入した方は限度額73万円となります)。
均等割の軽減
所得の低い方は、世帯(世帯主及び被保険者)の所得に応じて保険料が軽減されます。
保険料の被保険者均等割額負担軽減の基準
| 均等割額軽減割合 |
同一世帯内の被保険者および 世帯主の所得の合計額 |
軽減後の均等割額 |
|---|---|---|
| 7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等(※) の数-1)以下の世帯 |
14,220円 |
| 5割軽減 |
43万円+29万5千円×世帯の被保険者数+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
23,700円 |
| 2割軽減 |
43万円+54万5千円×世帯の被保険者数+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
37,920円 |
※給与所得者等とは、①一定額(55万円)を超える給与収入がある方、②一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金収入があり、給与所得がない方です。
※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得からさらに15万円が控除されます。
※軽減判定は、世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と、世帯主の所得の合計額が軽減判定の対象額となります。
※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯の状況で行います。
納付方法について
保険料の収め方には2種類あり、年金から天引きされる特別徴収(年金特徴)と、金融機関で納付する普通徴収の2種類があります。
特別徴収
| 仮徴収 | 本徴収 | |||||
| 納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
※4月1日に被保険者の資格をもっている方で介護保険料が差し引かれている年金が年額18万以上の場合は原則として年金からの天引きとなります。
普通徴収
| 期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納付月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
※年金特徴の判定のときに介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方、75歳に到達して後期高齢者医療制度に加入した初年度、年度の途中で他市町村から転入したとき、保険料額や年金額が変更になったときなども特別徴収ではなく普通徴収となります。
その他、詳しい制度の内容については後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。